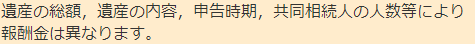お役立ち情報
相続税に関する特例や控除にはどのようなものがあるか
1 相続税に関する特例や控除の重要性
相続税に関して、ある特例が適用できる場合に、その特例をきちんと適用して申告することで、相続税の納税額が大きく変わってくることがあります。
また、同じく、相続税に関して、控除の適用ができる場合に、控除をきちんと適用して申告することで、やはり相続税の納税額が大きく変わってくることがあります。
そのため、相続税に関して主な特例は何か、主な控除は何かについて理解をしておくことが重要です。
2 相続税に関する特例
相続税に関する特例で、相続税対策で検討必須な特例は、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」といいます)です。
小規模宅地等の特例は、被相続人又は被相続人と生計を一にしている親族の事業又は居住用土地等の一定の面積までの部分の価格を80%又は50%減額できるという制度です。
小規模宅地等の特例は、特例の適用要件に該当した対象宅地等(所有権を有する宅地や借地権を有する宅地)のうちから、納税者が選択した宅地等で、面積要件を満たした宅地等に適用できます。
以下の4つに区分されています。
① 特定事業用宅地等
② 特定居住用宅地等
③ 特定同族会社事業用宅地等
④ 貸付事業用宅地等
上記の内、よく検討対象となるのは、被相続人が居住していた自宅に関する②の特定居住用宅地等と、借家物件をお持ちの方の④の貸付事業用宅地等となります。
特定居住用宅地等は、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等については、330㎡を限度として、80%を減額して相続税の算定の相続財産を評価することができます。
例えば、この特例を適用前の被相続人の自宅の宅地の評価が1億円(面積は330㎡)であった場合、この特例を適用できれば、相続税の計算においては2000万円で評価して計算すればよいことになります。
配偶者以外の者がこの特定居住用宅地等の適用を受けるためには、相続開始から申告期限までその宅地等を所有し続ける必要があります。
そのため、相続税申告前に相続税納税資金を準備するために、被相続人が居住していた自宅不動産を売却する場合、配偶者以外の相続人はこの特例の適用ができないことになるため注意が必要です。
貸付事業用宅地地等は、被相続人等の貸付事業に供されていた宅地等については、200㎡を限度として、50%を減額して相続税の算定の相続財産を評価することができます。
もっとも、特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等を併用適用する場合、適用面積の調整が必要となります。
特定居住用宅地等で330㎡、貸付事業用宅地等で200㎡と完全併用ができるものではないことは注意が必要です。
相続人等が1人の場合を除いて、申告書の期限までに共同相続人等の間で遺産分割が行われていない場合、特例の適用ができません。
もっとも、例外的に、相続税の申告を遺産分割未了の状態での未分割申告として申告書を提出すると同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、申告期限から3年以内に分割を行った場合、この特例の適用が受けられます(通常、特例の適用で申告税額が異なることになるため、修正や更正の申告を行うことになります)。
3 相続税に関する控除について
相続税に関する主な控除は、①配偶者控除、②未成年者控除、③障害者控除、④相次相続控除、⑤外国税額控除、⑥贈与税額控除です。
これらの控除によっても納税額が控除しきれない場合、相続税を納税する必要があります。
配偶者控除は、よく見られる控除であり、その控除額も大きなものになりえます。
配偶者控除は、以下の計算式で計算されます。
相続税の総額×B÷A
A:課税価格の合計額
B:配偶者の法定相続分相当額(1億6000万円未満の場合は1億6000万円)と、配偶者の課税価格との何れか少ないほうの金額
つまり、配偶者が遺産分割等で取得した相続財産の価格が1億6000万円までであれば、配偶者に相続税はかからないということになります。
未成年者控除や障害者控除は、相続人が未成年あるいは障害者である場合、当該相続人の相続税額から一定の税額が控除されるという制度です。
また、相次相続控除は、世代交代が短い場合、同じ相続財産に何度も相続税が科される不都合の対処のため、一定の税額の調整をする制度です。
外国税額控除も、外国で同じ相続財産に課税されている場合、日本国内でも同じように課税する場合には二重課税の負担が生じるため、その不都合の対処のため、一定の税額の調整をする制度です。
贈与税額控除も、既に贈与税を支払ったものに関して、その贈与税の対象財産が相続税において生前贈与加算等で課税価格に算入されることによる二重課税の負担の対処のため、一定の税額の調整をする制度です。
4 特例や控除の適用にあたって
相続税の小規模宅地等の特例の適用によって相続税は大きく異なってきますが、この特例の適用の検討は専門的な知識が必要な部分もあります。
また、控除についてもその適用の有無で、実際に支払う相続税の金額が異なることがあります。
相続税の申告に当たって、特例や控除をお考えの場合には、その適用の有無で相続税の納税額が大きく異なることもありますので、専門家の助力を得ることもご検討頂ければと存じます。
相続税で不服申立てをする場合 土地の形状によって相続税評価は変わるのか