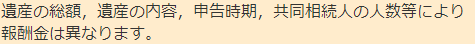お役立ち情報
相続税の2割加算とは
1 相続財産を取得した人によっては相続税が2割加算される
国税庁によれば、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるとされています。
参考リンク:国税庁・相続税額の2割加算
これだけでは分かりにくいので、以下、具体的な説明をします。
2 相続税の2割加算の対象となる人
相続税が2割加算されるか否かは、相続や遺贈によって相続財産を取得した方の属性によって決まります。
相続や遺贈(遺言による譲り受け)などで財産を受け取った人が、亡くなった方(被相続人)の一親等の血族及び配偶者以外である場合には、相続税額が2割加算されるとされています。
一親等の血族とは、被相続人の子と両親のことです。
ここでいう被相続人の子には、養子も含まれます。
注意すべきことは、孫を養子縁組した場合には、その孫も2割加算の対象になるという点です。
具体的に2割加算の対象となるのは、被相続人の兄弟姉妹、代襲相続人ではない孫、相続人ではない第三者などが挙げられます。
一親等の血族及び配偶者以外の方において相続税が加算される理由は、一親等の血族及び配偶者以外の方が相続財産を受け取るのは偶然性が高いため、および亡くなった方の孫が財産を相続すると、次世代である子の相続税を1回免れることになるためとされています。
3 相続税の2割加算の具体的な計算
相続税を計算する際は、まず相続財産の課税価額をもとに、相続税の総額を算定します。
そして、相続税の総額を、今度は実際に各相続人や受遺者が受け取った財産の割合に応じて割り振ります。
相続税の計算方法の具体例については、こちらもご参照ください。
2割加算の対象となる方においては、この割振られた後の各相続人等の相続税額について、2割を加算するという計算を行います。
例えば、代襲相続人ではない被相続人の孫養子に割振られた相続税額が100万円であった場合には、2割を加算し、納付すべき相続税額は120万円になります。
相続税申告の期限に間に合わないときの対応 相続税対策としての生前贈与での失敗例