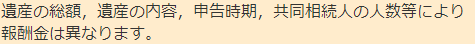お役立ち情報
相続税対策としての生前贈与での失敗例
1 相続税対策としての生前贈与の失敗例について
生前贈与は、相続税を節税する手法の代表的なもののひとつとして用いられることがあります。
特に、毎年贈与税の非課税枠の範囲内で相続人に対して贈与をする、暦年贈与が用いられることが多いです。
なお、相続開始前3年以内に贈与された財産(令和6年1月1日以降の贈与から段階的に7年の期間に延長)については、原則として相続税の対象となりうる点には注意が必要です。
参考リンク:国税庁・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
相続税対策としての生前贈与は、やり方を誤ってしまうと、生前贈与として認められず相続税が課税されてしまうことや、高額な贈与税が課されてしまうということも考えられます。
以下、具体的に説明します。
2 生前贈与として認められず相続税が課税されてしまう例
⑴ 名義預金とみなされるケース
親が子(推定相続人)の名義の口座を作成し、親が子に知らせずに、子の名義の口座に毎年贈与税の基礎控除以下の金銭を入金しているというケースは、実務上よくあります。
この場合、そもそも贈与が成立していないので、生前贈与がなされたことにならず、子の名義の口座に入っている金銭は、あくまでも親の金銭のままという扱いになります。
そのため、相続財産に含まれ、相続税の対象となります。
このような事態に陥ることを防ぐためには、生前に親と子の間で贈与契約書を作成し、贈与の意思表示があったことを証明できるようにしておくことが大切です。
⑵ 親が行為能力を失った後の贈与
認知症等になってしまったなど、親が法律上の行為能力を失っていたと考えられる状態でなされた法律行為は、一部の例外を除いて無効となります。
このような状況において、形式的に贈与をしたとしても、その贈与は無効であるため、贈与されたとされる財産は被相続人の財産に含まれ、相続税の対象となります。
3 高額な贈与税が課されてしまう例
毎年、贈与税の非課税枠の範囲内で贈与をするという手法は、相続税の節税対策として有効ではありますが、連年贈与とみなされないようにする必要があります。
例えば、毎年100万円を20年間に渡って贈与する場合について考えてみます。
これを、「2000万円を贈与し、毎年100万円ずつ支払う」と解釈すると、2000万円の贈与ととらえることもできます。
そうすると、2000万円の贈与に対する贈与税が課税されてしまう可能性があります。
このような事態になることを防ぐためには、毎年贈与契約をした事実を証明するために、毎年贈与契約書を作成するとともに、毎年の贈与金額や支払日についても、固定ではなくばらつきを持たせることが有効であると考えられます。
参考リンク:国税庁・贈与税がかかる場合
4 相続税対策としての生前贈与についてご相談ください
相続税対策として生前贈与を行うにあたっては、適切な方法で行わないと、有効な対策とならないばかりか、かえって税金の負担が大きくなってしまうこともあります。
相続税対策は、相続税に詳しい税理士と相談の上、適切な方法で進めていくことをおすすめします。
当法人では、相続税対策についてのご相談も承っており、相続税を得意とする税理士が対応します。
生前贈与で失敗しないよう、まずはお気軽にご相談ください。