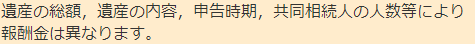お役立ち情報
生命保険による相続税対策
1 生命保険を利用すると相続税を低減できることがある
相続税の申告の際は、死亡保険金も相続財産とみなされ、相続税の課税の対象になります。
参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金
一方、死亡保険金には一定の非課税制度が存在しており、相続財産評価額を下げることができます。
この制度を利用し、相続税の節税をすることができる場合があります。
以下、具体的に説明します。
2 相続税の非課税制度の対象になる生命保険
実は、死亡保険金は、契約の内容によって異なる税金が課税されます。
相続税の非課税制度の対象になる生命保険は、被保険者と保険契約者が同じで受取人が異なるという内容の生命保険です。
例えば、被保険者と保険契約者が被相続人、保険金受取人が相続人の内のひとりとなっている生命保険です。
参考リンク:国税庁・死亡保険金を受け取ったとき
3 死亡保険金の非課税枠
死亡保険金の非課税制度には、限度額が存在します。
具体的には、次の計算式によって求められます。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
相続放棄した元相続人の方や、相続人以外の方が保険金取得した場合は、この非課税限度額の適用は受けられません。
法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に算入する養子の数は被相続人に実子がいる場合は1人、被相続人に実子がいない場合2人までとなります。
参考リンク:国税庁・相続人の中に養子がいるとき
また、相続放棄した人(はじめから相続人ではなかったことになる人)がいても、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数とします。
4 各相続人の非課税額の計算
相続人全員が受け取った死亡保険金の合計額が、3の非課税限度額以下である場合には、死亡保険金全額が非課税となります。
相続人全員が受け取った死亡保険金の合計額が、3の非課税限度額を上回る場合、次の計算で求められる金額が、各相続人の非課税限度額となります。
非課税限度額×(特定の相続人が受け取った死亡保険金の金額)÷(相続人全員が受け取った死亡保険金の合計額)
5 生命保険による節税対策をお考えなら税理士へ
上記のように生命保険を活用することで、相続税を減額できる場合がありますし、死亡保険金を残された家族の生活資金や納税資金として活用することも可能になります。
しかし、契約内容によっては相続税対策にならなかったり、かえって税の負担が増えてしまうこともあるため、慎重に対策を検討する必要があります。
相続税対策をお考えの方は、まず一度税理士にご相談ください。
相続税対策としての生前贈与での失敗例 不動産の活用による相続税対策のメリット